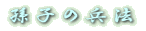
 |
|
| ■GzMap |
| ■三国志NET |
| ■三国志NET説明書 |
| ■掲示板 |
 
|
| 一、始計篇 |
|
兵は国の大事なり |
|
一に曰く道、二に曰く天・・・ |
|
兵は詭道なり |
|
能なるもこれに不能を示す |
|
その無備を攻め、その不意に出ず |
|
算多きは勝ち、算少なきは勝たず |
|
|
| 二、作戦篇 |
|
兵は迅速を聞く |
|
智将は務めて敵に食む |
|
敵の利を取るものは貨なり |
|
兵は勝つことを貴び久しきを貴ばず |
|
|
| 三、謀攻篇 |
|
用兵の法、国を全うするを上と為し |
|
百戦百勝は善の善なるものにあらず。 |
|
上兵は謀を伐つ |
|
小敵の堅は大敵の擒なり |
|
それ将は国の輔なり |
|
君の軍に患となる所以のものに三つあり |
|
勝を知るに五あり |
|
彼を知り己を知れば百戦殆からず |
|
| 四、軍形篇 |
|
勝つべからざるをなして、勝つべきを待つ |
|
善く戦う者は勝ち易きに勝つ |
|
勝兵は鎰を以って銖を称るがごとく・・・ |
|
|
| 五、兵勢篇 |
|
衆を治むるが如く寡を治むるが如く |
|
戦いは正を以って合し、奇を以って勝つ |
|
戦勢は奇正に過ぎざるも、奇正の変は勝げて窮むべからず |
|
善く戦う者は、その勢は険にしてその節は短なり |
|
善く戦う者は、これを勢に求めて人に責めず |
|
|
| 六、虚実篇 |
|
戦地に処りて敵を待つ者は佚し、後れて戦地に処りて戦いに趨く者は労す |
|
善く戦う者は人を致して人に致されず |
|
攻めて必ず取る者は、その守らざる所を攻むればなり |
|
微なるかな微なるかな無形に至る。神なるかな神なるかな無声に至る。 |
|
進みて禦ぐべからざるものは、その虚を衝けばなり |
|
われは衆にして敵は寡なり |
|
寡とは人に備うるものなり。衆とは人をして己に備えしむるものなり |
|
戦いの地を知り戦いの日を知れば、千里にして会戦すべし |
|
勝は為すべきなり |
|
兵を形するの極は、無形に至る |
|
それ兵の形は水に象る |
|
|
| 七、軍争篇 |
|
人に後れて発して人に先んじて至る |
|
諸侯の謀を知らざる者は、予じめ交わること能わず |
|
兵は詐を以て立ち、利を以て動き、分合を以て変を為すものなり |
|
その疾きこと風の如く・・・ |
|
迂直の計を先知する者は勝つ。これ軍争の法なり |
|
言えどもあい聞こえず、故に鼓鐸を作る。 視せどもあい見えず、故に旌旗を作る。 |
|
善く兵を用いる者は、その鋭気を避けてその惰帰を撃つ |
|
|
| 八、九変篇 |
|
九変の利に通ずる者は、兵を用いることを知る |
|
智者の慮は必ず利害に雑う |
|
その来たらざるを恃むことなく、われのもって待つあることを恃むなり・・・ |
|
将に五危あり |
|
|
| 九、行軍篇 |
|
およそ四軍の利は、黄帝の四帝に勝ちしゆえんなり |
|
およそ軍は高きを好みて下きを悪くみ、陽を貴び陰を賤しむ。 |
|
上に雨ふりて水沫至らば、渉らんと欲する者は、その定まるを待て |
|
およそ地に絶澗、天井、天牢、天羅、天陥、天隙あり、 必ず亟かにこれを去りて、近づくことなかれ |
|
軍の旁に険阻、?井、葭葦、林木、?薈ある者は、必ず謹んでこれを覆索せよ。これ伏姦の処る所なり |
|
兵怒りてあい迎え、久しくして合わず、 またあい去らざるは、必ず謹みてこれを察せよ |
|
兵はますます多きを貴ぶにあらざるなり |
|
卒いまだ親附せざるに而もこれを罰すれば、服せず |
|
令のもとより信なるは衆とあい得るなり |
|
|
| 十、地形篇 |
|
地形には、通なるものあり、 挂なるものあり、支なるものあり、 隘なるものあり、険なるものあり、遠なるものあり |
|
兵には走なるものあり、弛なるものあり、陥なるものあり、崩なるものあり、乱なるものあり、北なるものあり。 |
|
それ地形は兵の助けなり |
|
進んで名を求めず、退いて罪を避けず、 ただ民をこれ保ちて利の主に合うは、国の宝なり |
|
卒を視ること嬰児の如し |
|
彼を知り己を知れば、勝、すなわち殆からず |
|
|
| 十一、九地篇 |
|
兵を用うるの法は散地あり、軽地あり、争地あり、交地あり、衢地あり、重地あり、?地あり、囲地あり、死地あり |
|
利に合して動き、利に合せずして止む |
|
まずその愛する所を奪わば、則ち聴かん |
|
死いずくんぞ得ざらば、士人力を尽す |
|
往くところ無きに投ずれば諸?の勇なり |
|
手を攜うること一人を使うがごとし。已むを得ざらしむるればなり |
|
将軍の事、静をもって幽、正をもって治 |
|
およそ客たるの道、深ければ専らに、浅ければ散ず |
|
四五の者、一を知らざるも覇王の兵にあらざるなり |
|
それ覇王の兵、大国を伐てば、その衆聚まることを得ず |
|
それ衆は害に陥りて、然る後によく勝敗をなす |
|
始めは処女の如く、後は脱兎の如し |
|
|
| 十二、火攻篇 |
|
孫子曰く、およそ火攻に五あり |
|
おそよ火攻は必ず五火の変に因りてこれに応ず |
|
火をもって攻を佐くる者は明、水をもって佐くる者は強 |
|
それ戦勝攻取して、その功を修めざる者は凶、命づけて費留と曰う |
|
主は怒りをもって師を興すべからず。将は慍りをもってて戦を致すべからず |
|
|
| 十三、用間篇 |
|
俸禄百金を愛みて敵の情を知らざる者は、不仁の至りなり |
|
間を用うるに五あり |
|
微なるかな微なるかな、間を用いざるところなきなり |
|
反間は厚くせざるべからざるなり |
|
明君賢将、よく上智をもって間を為す者は必ず大功を為す |
|
|
|
HP素材:三国志Drive様 |
|
HP素材:綺陽堂様 |
